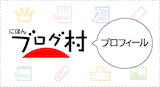\歴史好きにオススメ/
目次
見えない力を信じすぎた男

「見えない力を信じますか?」
戦国時代、「知略と武略」がすべてではありませんでした。
その裏には「呪術」や「占い」といった、目に見えない力を使う武将もいたのです。
その力を利用した男が細川政元(ほそかわ・まさもと)です。
彼は自らを「半僧」と名乗り、陰陽道や加持祈祷を政治の要とした
「日本オカルト大名の代名詞」
なのです。
合理性・論理性が正義である現代
その政治能力は確かに奇異に見えるかもしれません。
しかし、500年前の政元もまた、私たちと同じように「誰かに頼りたい」「選ぶべき道は何か」と迷った一人のおじさんなのです。
ここでは、政元の人生を通じて、「信念とは何か」「信じぬくとはどういうことか」を、歴史エピソードとともに深掘り
人生のヒントに
あるいは
反面教師として
あなたの人生の選択肢を増やす参考にしていただければ幸いです。
戦国オカルト政治を体現した異端のリーダー
戦国時代と聞けば、織田信長や武田信玄、豊臣秀吉のような“武力で天下を狙う猛者”たちを思い浮かべる人が多いかもしれません。
でも、その裏で「見えない力=呪術」や「陰陽道」を使って政治を動かそうとした武将がいたのをご存じでしょうか?
その代表格が、細川政元(ほそかわ まさもと)という人物です。
政元は、室町時代後期に幕府の実権を握った「管領」という立場にあった名門・細川家の当主。
一見、エリート中のエリートですが、実はかなりの変わり者。
なんと自分で「半僧(はんそう)」と名乗って出家しつつ、陰陽師を重用し、占いや呪術を政治の判断材料に使っていたのです。
例えば、戦の開始時刻や出陣日もすべて陰陽道に従って決定。
政元にとって政治とは、合理性よりも「運気」や「方角」がすべてでした。
さらに驚くのが、彼が「将軍を決める」ほどの力を持っていたこと。
自らの意志で足利義材を追放し、新たな将軍として足利義澄を擁立するなど、まるで“将軍メーカー”。
まさに、陰陽道と政略の力で、室町幕府を事実上コントロールしていた存在です。
しかし、そんな異端の政治はやがて家中の不満を招き、家臣のクーデターによって命を落としてしまいます。
最期もまた、陰陽師から「凶兆あり」と占われていたにもかかわらず、それを振り切って動いた結果だったと伝わります。
つまり細川政元は、戦国史の中でも「合理では割り切れない信念」を貫いた希少な人物。
彼の生涯は、「信じる力が人を動かす」ことの可能性と危うさの両方を私たちに教えてくれるのです。
政元は、将軍家を操る「管領」に任ぜられることで権力を得ます。
当時の将軍庁は形骸化していましたが、管領は事実上の政治実権を握ったのです。
室町幕府第10代将軍・足利義材(よしき)を追放し、11代将軍として義澄を擁立。
これにより細川家の影響力は一層強まります。
絶大な力を呪術や占いを多用することで得た細川政元。
では一体どのような呪術や占いで政治を動かしたのでしょう。
次に具体的なエピソードを見ていきましょう。

重要事項はすべて占星術で決定!
政元にとって、政治のすべては「吉凶を占うこと」から始まりました。
- 出陣日時:方角・日時を陰陽師に占わせて決定。
- 人事対立:対立候補者には「凶相を呼ぶ呪詛」をかけたと噂。
- 屋敷・城造営:風水に基づいて間取りと配置を設計。
特に重要だったのは、政元が参拝した護王神社(現京都)において、毎年行われる火焚祭で「王法を護る祈祷」を欠かさなかったことです。
ここでの占いや祈りが、政治判断に直結していたと言われます。
天狗になりたかった政元

まず驚かされるのが、政元が「天狗」に強い憧れを抱いていたことです。
伝説の英雄・源義経が鞍馬山で天狗から兵法を授かったという逸話に、自らの姿を重ねていたと言われています。
実際、安芸国の宍戸氏出身で修験道に通じた司箭(しせん)という人物を師と仰ぎ、彼を「天狗の化身」とみなしていたという話も残っています。
現代人からすれば「厨二病か!」とツッコミたくなるような話ですが、当時は霊的な存在が現実の政治や戦に影響を与えると本気で信じられていた時代。
政元はその思想を極限まで体現した存在だったのです。
「烏帽子はダサい」と断固拒否!?
政元は、当時の武士の正装である烏帽子(えぼし)をかぶるのを頑なに拒否しました。
これには周囲の幕臣たちも困惑。
なにせ、公式の場で頭に何も被らないというのは、大名としては異例の振る舞いだったからです。
また、将軍を補佐する最高位の職「管領」に任命されても、数日も経たないうちに「面倒だ」と辞退。
これを何度も繰り返しました。
形式的な地位や服装にこだわらず、実際の権力さえ握っていればいい。
政元は、そう考えていたのかもしれません。
あるいは単に「型にはまるのが嫌い」な天の邪鬼だっただけなのかもしれません。
ただ、それすらも政治的な演出だったとも取れるのが彼の奥深いところです。
比叡山に攻撃!? 信長よりも早かった宗教弾圧

戦国時代の象徴的事件として知られるのが、織田信長による比叡山延暦寺の焼き討ちです。
しかし、実は比叡山焼き討ちを最初にしたのが細川政元だったという説があります。
当時、敵対していた足利義材をかくまった延暦寺に対し、政元は激怒。
兵を率いて比叡山を攻撃し、主要伽藍である根本中堂などを焼き払ったとされます(ただし、これについては記録によって意見が分かれています)。
政元にとっては、宗教の威光すら自身の政治の妨げになれば排除すべき対象でした。
ここでも彼の「信仰」と「実利」のバランス感覚が独特な形で現れています。
呪詛を唱える政治家
さらに異彩を放つのが、政敵に対して“呪いのお経”を唱えたという逸話です。
声高に経文を読み上げ、その中には明らかに呪詛の意図が込められていたと言われています。
「呪いで政敵を倒す」
今では、フィクションの世界です。
しかし当時の人々は本気でそれを恐れました。
政元は、この“恐怖”を武器に政治的な影響力を高めていたとも考えられます。
狂気か、それとも信念か。。
細川政元の中に宿っていたのは、狂気か、それとも信念か。
陰陽道と呪術を武器に政治を操った彼の生涯は、常識を超えた狂気のようでありながら、「見えないものを信じる力」がいかに強いかを教えてくれます。
誰もが日頃
朝のテレビ番組で今日の占いを見てしまう。
順位が上であれば、なんだかテンションが上がってしまう。
逆に順位が下であれば、今日は気をつけようと心構える。
世界は占いでできているのかも知れません。
それは、おじさんたちにとっても例外ではないのです。
誰もが、見えないものを信じてしまう。
人とは、そのような危うさと心細さを併せもっているのです。
その心理を上手く利用したのが細川政元なのかも知れません。
ここまでで、彼を単なる風変わりな大名と考えるかも知れません。
戦国時代とは、武士の権威や幕府の権力が揺らぎ、古い秩序が崩れ始めていた時代。
そんな中で、既存の価値観に風穴を開けようとした政元の姿勢は、ある意味では時代の先を見ていたとも言えます。
自らの“異質さ”をあえて演出し、周囲に一目置かせる戦略。
形式を嫌い、本質だけを握ろうとする感性。
そして、信仰と現実を自在に行き来する柔軟さ。
これらは、決して「風変わりな人物」だけが持ち得るものではありません。
むしろ、政元は「非常識の中にこそ真理がある」と信じていた、したたかな現実主義者だったのかもしれません。
この記事で、誰かの何かに刺さっていたら幸いです。