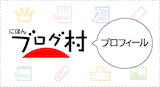\大名の趣味世界/

目次
江戸オヤジ大名たちは「究極の趣味人」だった!
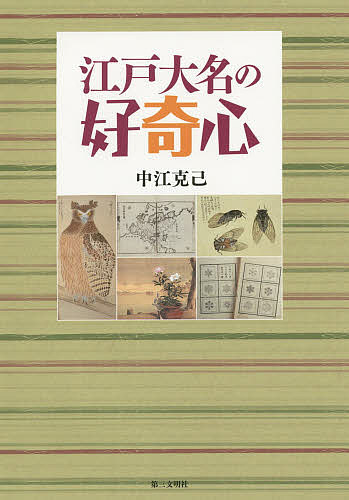
「趣味って、男の人生をワンランク上にするんよなぁ」
そんな会話を交わしたことを一度はあるはずです。
仕事一筋で突っ走ってきた人ほど、定年が近づくと「で、これから何する?」と自問する瞬間がやってきます。
江戸時代の大名たちも同じように考えたのではと思っています。
戦国のヒリヒリした日々が過ぎ去り、平和な時代が到来すると、「刀と鎧」というアイテムから「筆と盆栽」というアイテムへと出世の道具がかわったのです。
実は、江戸のオヤジ大名たちは驚くほど多趣味でした。
あるオヤジは珍獣を飼い愛でる
また違うオヤジは盆栽に心を注ぎ、鉱物や絵画を集めました。
時には趣味を外交の道具にしてしまうオヤジ達もいました。
これらは単なる娯楽ではなく、政治的な戦略や家の威信を示すための重要なツールでもあったのです。
そして
「趣味の世界」とは、江戸時代のオヤジ大名と同じく、我々おじさん世代にも通じるエッセンスがゴロゴロ転がっています。
例えば
- コレクションは人間関係を深める潤滑油になる
- 趣味には自分の価値観や美意識が現れる
- 集めた物の背景を知ると、さらに愛着が湧く
今回は、江戸時代のオヤジたちの趣味をテーマに、「動物」「鉱物」「盆栽」「趣味外交」といった切り口で歴史を深掘りしていきます。
戦国武将たちが命を懸けたのは戦だけではありません。
平和の世になると、その情熱を趣味に燃やしたのです。
あなたが今、何かに夢中になっているなら、江戸の趣味人たちはきっと共感してくれるはず。
そして、まだ趣味を探している人には、「これ面白そう!」と背中を押すきっかけになるかもしれません。
「趣味が政治になる」江戸オヤジ大名の趣味外交!!
戦国時代、武士の評価は「戦場での武功」で決まりました。
しかし、徳川家康が天下を取ってからは戦の機会が激減。
大名たちは江戸や国元での「暮らしの質」や「文化的教養」が重要視されるようになります。
ここで趣味が大きな意味を持ちました。
書画、茶道、香道、武芸、園芸…趣味は「その人の格」を示すパスポートであり、人脈形成の重要なツールとなります。
特に参勤交代の合間、大名たちは屋敷に趣味専用の座敷や蔵を設け、同好の士を招いて語り合いました。
現代のビジネスマンが高級腕時計やワインコレクションを話の種にするのと同じです。
趣味は自分を語るための「もう一つの名刺」なのでした。
では
江戸時代の大名は、一体どのような趣味で政治に活かしたのでしょう。
江戸オヤジ大名たちの趣味を一部覗いてみましょう!
\大名の趣味世界/

米将軍は珍獣コレクターだった!?

江戸の大名の中には、珍しい動物を集めて楽しむ“動物園好き”タイプがいました。
代表格は八代将軍・徳川吉宗。
享保の改革で有名ですが、実は動物好きでも知られます。
享保14年(1729年)、清(中国)から雄の象を輸入し、江戸城で飼育したそうです。
この象は江戸庶民の大人気となり、見物客が押し寄せました。
まさに「将軍の権威」を見せつける役割を果たしたのです。
また、
松平定信はオウムやインコなど南蛮渡来の鳥を愛好。
海外貿易でしか手に入らない鳥を所有することは
国際的なコネを持つ
あるいは
自分の権威を他に知らしめるといった役割がありました。
珍獣コレクションは、今でいうところの「高級外車コレクション」に近い感覚。
希少性と話題性がステータスを作るといった効果があったのでした。
独眼竜は石に魅せられた!

江戸の大名の中には、石や鉱物の魅力に取りつかれた者もいました。
伊達政宗は領内の鉱山開発を進める傍ら、鉱物や奇石を収集。
黄金や銀はもちろん、水晶や瑪瑙など美しい石を愛でました。
政宗にとって石は「富と権力の象徴」であると同時に、風水的な意味を持つ縁起物でもありました。
また、肥後細川家では「奇石展覧会」を開催した記録が残っており、石を愛でる文化は武士の間でも静かなブームになっていました。
これは
おじさんがパワーストーンを手にするのと似ていて、当時の武士も「石には力が宿る」と信じていたのです。
あるいは
ゴツい指輪やネックレスを収集する気持ちに似ているのかも知れませんね。
もし
伊達政宗が現代にいたら、きっと悪いオヤジ風ファッションを好んでいたことでしょう。
盆栽・盆景は小宇宙!徳川斉昭の嗜み

大名の趣味として欠かせないのが盆栽や盆景。
盆栽は単なる植物ではなく、自然を凝縮した“小宇宙”であり、武士の精神修養にもつながりました。
盆栽・盆景を趣味にした大名で特に有名なのが水戸藩第9代藩主・徳川斉昭。
彼は、盆栽を「武士の嗜み」と位置づけ、武士道精神を体現するものとして奨励しました。
そして藩主自らが盆栽の手入れを行ったとされます。
また松や梅を数十年かけて育て、その枝ぶりに「自らの人生」を重ねる大名もいました。
盆栽は忍耐と計画性を要求します。
これは戦国武将が培った戦略眼にも通じるもの。
現代のおじさんがゴルフや釣りで時間を忘れ、戦略を練るように彼らも盆栽に没頭したのです。
そして趣味は外交の武器に!
江戸大名にとって趣味は社交の道具でもありました。
茶の湯を嗜む大名は、茶器や掛け軸を見せ合いながら同盟を結びました。
また刀剣愛好家は名刀の貸し借りを通じて信頼を深めたのです。
つまり
趣味は単なる娯楽ではなく、実利をもたらす“外交ツール”“政治ツール”だったのです。
現代も、ゴルフやワイン会、模型サークルを通じて人脈を築くことがあります。
それがビジネスに直結することもあります。
集客するには、趣味サークルに属した集客が1番良い方法。
なんて言うコンサルタントもいるほどです。
江戸の趣味外交は、それと同じ発想だったと言えるでしょう
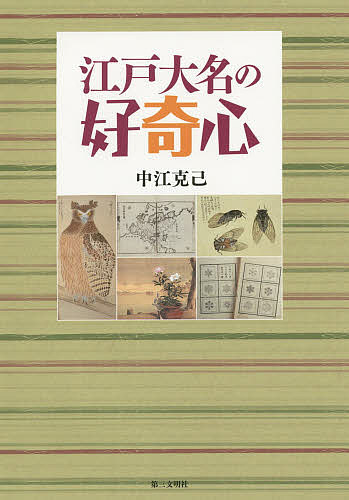
江戸オヤジから学ぶ趣味の活かし方
江戸オヤジたちの趣味には、現代にも通じます
- 趣味は孤独を癒やす:一人で没頭できる時間が心を整える
- 趣味は人脈を広げる:共通の話題が信頼関係を築く
- 趣味は自分を映す鏡:何を選び、どう楽しむかに性格が現れる
江戸オヤジたちは趣味を通して人生を豊かにし、家の威信を高め、人との絆を育てました。
現代のおじさんも、同じように趣味を通して第二の人生を輝かせることが大事なのではと思っております。
江戸時代の大名たちは、戦国のような血なまぐさい日々から解放され、趣味という「もう一つの戦場」に情熱を注ぎました。
珍獣を飼い、奇石を集め、盆栽を育て、茶室で政治を動かす──これらは一見バラバラに見えますが、根底にあるのは「自分らしさをどう表現するか」という問いです。
それは、いつの時代も同じです。
定年後の時間
子育てが一段落した後の時間
あるいは日常のちょっとした隙間時間
あなたは何をして過ごしますか?
江戸大名の趣味から学べるのは、「趣味は物そのものより、そこに込めた物語が大事」ということ。集めた盆栽一本にも、「誰から譲られたのか」「どんな育て方をしたのか」という物語があり、それが価値を倍増させます。
つまり
趣味にも物語が大事
という事ではないでしょうか。
\大名の趣味世界/

もしかすると、今あなたが飾っている骨董品や釣り道具、プラモデルにも、未来の誰かに語り継がれる物語が眠っているかもしれません。
江戸のオヤジたちは、自分の人生を豊かにするだけでなく、その趣味を通して家や地域にまで影響を与えました。
我々、おじさんたちも趣味をただの消費で終わらせず、「文化」に昇華させることができるはずです。
趣味は人生のスパイスであり、時にメインディッシュにもなります。
江戸オヤジたちの生き様を参考に、あなたも“趣味人”としての道を歩んでみてはいかがでしょう!