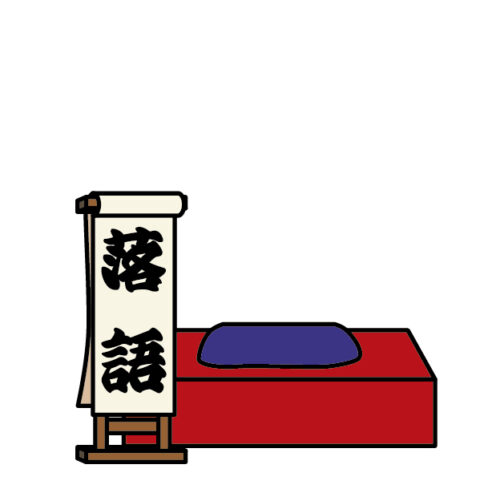目次
落語といえば「浅草」

日常に落語がある街。
落語の中心地であり聖地。
それが浅草です。
最近、アニメや漫画で人気になっている落語ですが、落語は庶民の娯楽であり、初心者でも楽しめるエンターティメントなのです。
そんな落語の聖地、浅草に戦後、中心人物となった三人の天才落語家が古今亭志ん生・三遊亭圓生・桂文楽です。
それぞれ違った魅力のある三傑の人生と魅了してやまない芸である落語に少し言及しながら、浅草の良さに触れてみようと思います。
昭和が産んだ天才落語家の生き様に触れて、落語を身近に感じる旅に出かけてみましょう。
昭和の名人三傑の生き様
戦争から解放され、復旧へとガムシャラに励んでいた昭和の日本人は、笑いに飢えていました。
その中で浅草という煌びやかな世界で、古くから伝わる話芸である「落語」を飯の種にし、人々に笑いを提供した三人の天才がいました。
昭和の名人と称えられた三傑の人生を、それぞれ振り返ってみようと思います。
・5代目古今亭志ん生
・生い立ち
1890年(明治23年)志ん生は、先祖が菅原道真を称する徳川家直参旗本の美濃部家の御曹司として、東京で生まれます。
とはいえ、志ん生の父親の代には、すっかり零落していて貧乏暮らしでした。
志ん生の唯一の娯楽は、父親が連れて行ってくれる寄席通い。
その後、志ん生は、放蕩暮らしの毎日の自堕落な青年になります。
幼少期の寄席通いが楽しかったのか、その頃から芸事に興味を示します。
元々、人の下で働くのが嫌な性分で、師匠をコロコロとかえ、1921年(大正10年)真打ちに昇進します。
真打ちに昇進した翌年、結婚し、幸せな生活を送ると誰もが思っていましたが、頑固な性格が仇となり、落語会の重鎮に楯突き、居場所を無くします。
落語の実力はあるが、愛想も愛嬌もなく、周囲と上手く合わせられない性格により、生活は極貧状態になります。
その頃の志ん生は、前座の寄席仕事・場末の寄席仕事を廻って、どうにか生活をしていった状態です。
ようやく志ん生の実力が大衆に認められ、ようやく人気を博すのが昭和初期の頃です。
師匠をコロコロ変え、改名すること16回ほど。
型にハマらない志ん生独自の型が魅力の話芸は、この紆余曲折の経験があったからこその賜物です。
志ん生の落語は、いわゆる、客を選ぶ芸です。
当然、嫌いな方は徹底的に嫌い、好きな方はとことん好きという両極端が魅力の落語家となるのです。
6代目三遊亭圓生は「志ん生とは道場の試合では勝てるが、野天の真剣勝負では斬られるかもしれない」と志ん生の芸について言及しています。
我流の極み。
5代目古今亭志ん生の落語の魅力は、そんなところにあるのでしょう。
・持ちネタ落語
古今亭志ん生は、持ちネタ・得意ネタの多さでも有名ですが
・火焔太鼓
・居眠り佐平治
・粗忽長屋
・替り目
数えるとキリがないほどです。
その独特かつスピード感があり、色気と品を感じさせる語り口は、今だに多くのファンを虜にする名人落語です。
古今亭志ん生が亡くなった時に、東京落語が終わったと言われたほどの名人芸!
▼是非、拝聴してください▼
・6代目三遊亭圓生
・生い立ち
1900年(明治33年)に大阪で生まれた圓生は、両親が離婚すると東京に移住しました。
東京に移住後、程なくして母親が、5代目三遊亭圓生と再婚します。
5代目三遊亭圓生を「親父」と呼び、義理ではあるが親子関係は良好だったようです。
幼少期より記憶力が良く、他の落語家の高座を見聞きするだけで、噺を覚えたという程、落語の神様に愛された人物です。
その後、生活が苦しく、一度は落語の世界から足を洗おうとするのですが、5代目圓生が亡くなると、6代目三遊亭圓生を就任することになります。
芸事には、一切の妥協を許さず、稽古熱心で知られる圓生は、新作落語を嫌い、古典落語至上主義の落語家だったそうです。
しかし、メディアへの出演は先進的な考え方の持ち主であり、ラジオやテレビに積極的に出演しました。
芸人仲間の好き嫌いが激しく、思ったままに話すことから、落語は名人であるが、人間性は否定されることが多かったのも事実です。
芸に厳しく、金銭に細かい、機嫌の浮き沈みが激しい圓生は、人に恐れらこそすれ、愛されることは少なかったように思えます。
また女性関係も激しく、昭和の芸人然とした落語家であったのでしょう。
前述の三遊亭志ん生は、「まんべんなく人物描写をしているが、それだと噺にヤマが出来ない。主人公だけ浮き彫りにさせてやらなきゃ駄目だ」と圓生の芸を酷評しています。
どちらも名人ですが、競争心も旺盛な二人だったのでしょう。
・持ちネタ落語
幼少期から記憶力が抜群であった圓生の持ちネタは、落語家史上最多ではないかと言われるぐらい持ちネタ・得意ネタが多いのが特徴です。
人情噺から滑稽噺、音曲噺、芝居噺、さらには怪談噺まで非常に幅広いジャンルを演じた昭和のモンスターです。
また幼少期からの落語家である圓生は、芸歴も長く、明治の落語家を彷彿とさせる洗練されたレトロ感も秀逸です。
三遊亭圓生の、時には軽々と時には色気たっぷりと緩急をつけた落語は、聞く者を魅了してやみません
▼何を聞いても一級品の落語を是非ご賞味ください▼
・8代目桂文楽
・生い立ち
1892年(明治25年)生まれの文楽は、並河家という常陸国宍戸藩主・松平家の家来筋という立派な武家の出です。
幼くして父親を亡くし、貧乏な家計により、奉公に出された文楽ですが、夜遊びが過ぎて放蕩三昧の暮らしぶりだったようです。
職を転々としますが、どれも物にならず、しばらくプラプラしていたが、義父の紹介で落語家の道に進みます。
そして3代目三遊亭 圓馬(さんゆうてい えんば)に師事し、落語のイロハを徹底的に教えてもらいました。
圓馬は、晩年、病気により、言葉が不自由になりましたが、文楽は生涯、尊敬してやまない師匠として崇拝し続けました。
その後、5代目柳亭左楽に師事し、真打ちに昇進します。
この左楽には、落語よりも政治力や帝王学を学んだおかげで、後年の文楽は、落語協会のトップとして長く君臨できたそうです。
ちなみに、桂文楽襲名は6代目の襲名であったが、末広がりが縁起が良いということで8代目桂文楽襲名としたそうです。
そして桂文楽といえば、最後の高座が伝説になるほど有名です。
演目「大仏餅」の登場人物・神谷幸右衛門の名が出ず絶句した文楽は
「もう一度勉強しなおしてまいります」の言葉を残し、二度と高座に上がらなかったのです。
・持ちネタ落語
自宅住所が黒門町であったことから「黒門町」や「黒門町の文楽」と呼ばれていた8代目桂文楽。
持ちネタの数は、それほど多くはなかったですが、一つ一つを丁寧に練り上げ、至高の落語として作り上げています。
代表的な落語といえば
・明烏
・愛宕山
・素人鰻
・船徳
などでしょうか。
▼桂文楽が磨きに磨いた、これらの落語は、文楽が現役でいる間は、誰も高座にかけなかったという▼
▼昭和の名人芸に震えて、聞いてください▼
▼落語の始祖と呼ばれ、豊臣秀吉を翻弄した戦国時代の有名な人物もいます▼
▼落語家に興味が出る記事は▼
落語帰りは、浅草土産で!
下町情緒溢れる浅草は、昭和を感じさせるノスタルジックな雰囲気とレトロ感満載の街です。
古き良き日本を感じさせ、創業100年以上も続く老舗店が軒を並べる、愛すべき浅草を堪能してみませんか。
落語といえば浅草だけど、落語だけではない浅草を感じさせる土産の代表例をご紹介いたします。
・芋ようかん
さつま芋の皮を丁寧に手で剥き、素朴な味に仕上げた浅草土産定番の芋ようかんです。
飽きのこない味は、老若男女問わずファンの多い逸品。
甘さを抑えたこし餡を寒天で包み込んだ、あんこ玉も人気で「小豆」「白いんげん」「抹茶」「苺」「珈琲」「みかん」の6種類を楽しめます。
・雷おこし
浅草のシンボルである「雷門」に由来するお菓子で、浅草を代表するお土産です。
「おこし」という非常に吉兆のある名前は、お祝いごとにも最適なお菓子です。
個包装にもなっていますので、一口サイズで食べやすさも人気の秘密です。
昔ながらのサクサクとした食感と味は、無性に食べたくなるクセになる銘菓です。
・七味唐辛子
こちらも浅草土産の定番の七味唐辛子。
日持ちを心配する方には、最適な浅草土産です。
昔ながらの工程にこだわり抜き、えも言われぬ香味と辛味が混ぜわさり、絶品の旨味となっております。
・江戸切子
特別な日に、特別な人に、江戸切子を送ってみるのも一興かと思います。
江戸切子は、江戸時代に海外から持ち込まれたガラスに、職人が細工をつけ始めたのが最初といわれています。
市井から生まれた伝統工芸品は、今や日本の伝統工芸品に指定されるまでの至る芸術へと昇華した逸品となりました。
・手ぬぐい
お菓子以外のお土産に悩まれている方には、手拭いがオススメです。
非常に実用的でもあり、和を感じさせる手拭いは、質感や手触りなども上質です。
和ティストの他にも、さまざまな模様と種類がある手拭いは、特に海外の方にも喜んでもらえるお土産ではないでしょうか。
破天荒な芸人に寛容な昭和という時代

急速な近代化と文化の変革期が盛んだった昭和という時代。
俗にいう「ノム」「ウツ」「カウ」の破天荒な芸人が受け入れられ、歓迎された時代でもあります。
また、社会の目まぐるしい変化の中で、テレビが普及したことにより、人々は新しい笑いや娯楽を追求し、破天荒な芸人を求めた時代でもありました。
クセのある芸人の多彩な才能と個性に寛容で自由な時代が昭和という時代であり、昭和という時代がなければ、日本は面白みのない場所になっていたのかも知れません。
昭和を代表する3人の落語家は、昭和という時代がなければ、輝くことがない落語家であり、破天荒な落語家を受け入れる多様性を持った場所がなければ、行き場がなかった落語家です。
それがエンターティメントの聖地「浅草」という場所だったのではないでしょうか。